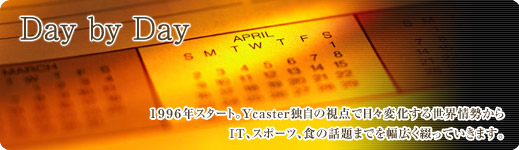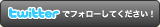(10:24)バイカル湖はでかいですよ。改めて書きますが、「日本の面積の10分の1」ある。琵琶湖の50倍。よく見ると、それは日本の本州の形によく似ている。月が欠けた形とも言える。三日月型なのでその巨大さにもかかわらず、狭いところでは対岸が見える。特に冠雪の山は。
何よりも驚くのは、「世界の淡水の25%をこの湖が持つ」とされる点だ。これは凄いことじゃないですか。「ロシアにはそんな資源もあるのか」と思う。もともとは深海が陸に囲まれたまま隆起し、淡水化したとされる。出来たのが2500万年前で、「世界最古の湖」かつ「世界最大の淡水湖」だそうだ。
深い海だったので、今でも湖でもっとも深いところは水面から1637メートルに達するとされる。この辺の標高(海抜)はせいぜい450メートルだから、バイカル湖の湖面から見て下に尖ったコーン(いや出刃包丁)のようになっている湖底は、海面よりかなり下と言うことになる。もし地下水脈があれば、今でも多少の塩が混ざってもおかしくない。私の勝手な想像だ。近く変動で、バイカル湖は毎年1センチ幅を広げているという。
昨日線路沿いにずっと(考えたら列車は3時間近くバイカルの湖岸を走っていた)見ていたバイカル湖は、風が強かったせいか濁っていた。しかし冬は透明度が高まるのだそうだ。「43メートル先が見透せる」時もあると書いてある。その時は、「世界一二の透明度の高い湖」だという。
驚くのは、固有種として「アザラシ」がいることだ。湖にアザラシがいるというのが、凄い。あと1500を超える固有種が住んでいるそうだ。冬は全面凍結するという。きっと寒いのだろうな。
しかし、バイカル湖が全面的に結氷している姿も見て見たい。「御神渡り」はあるのだろうか。あるとすると、凄まじい音がすると思う。しかし日本でも長野県の諏訪湖以外に「湖の氷が氷結し、ある程度進んだ段階で氷全体が盛り上がって線を作りながら割れる」という話はあまり聞かないので、無いのかも知れない。(と思ったら、ターニャがバイカル湖にも氷が割れて盛り上がる、と言っていた。凄い音だろうな)
これは私が勝手に考えたのだが、「バイカル湖は世界の湖の中で、一番人の命を数多く飲み込んだ湖かも知れない。知られているだけで25万人のロシア革命時の泊軍の人々(貴族やその軍隊)が湖底に沈んでいる。その他にもこの湖にはいろいろな悲劇が伝わる。だから、句にも詠んでみた。今日これからバイカル湖はゆっくり見る。
 イルクーツクには、昨日の夕方6時10分に着いた。ロシアの駅舎は、ウラジオストックがみすぼらしかったが、その他は結構堂々としていて綺麗だ。日本の駅舎が絶対使わない色をしている。白が基調で、そこに薄いブルーを使ったり、草色を使ったり。ハバロフスクの駅舎は綺麗だったが、イルクーツクの駅も良い。冬見れば、また違った趣があるのかも知れない。
イルクーツクには、昨日の夕方6時10分に着いた。ロシアの駅舎は、ウラジオストックがみすぼらしかったが、その他は結構堂々としていて綺麗だ。日本の駅舎が絶対使わない色をしている。白が基調で、そこに薄いブルーを使ったり、草色を使ったり。ハバロフスクの駅舎は綺麗だったが、イルクーツクの駅も良い。冬見れば、また違った趣があるのかも知れない。
街は綺麗だ。実は明日、イルクーツクは建設されてから350年の記念日に当たるという。日本の多くの都市のように、「気がついたら出来ていた」というのとは違う。「誰がいつ、誰の命令で入植して」というのが分かっているのだ。ロシアは意図的に東方進出を図った。
この街のガイドであるターニャさんによれば、この街は大火(1879年)に1度見舞われた。その前は家々は全部木造だったそうだ。しかし大火のあと、家や建物は石造りに切り替えられたそうだ。そして、この古い町には当時(100年以上前)に建設された古い建物が大部分残っているという。ナポレオンもヒットラーも、この街には遠く及ばなかった。
この街を愛したのはチェーホフだ。彼がイルクーツクを「シベリアのパリ」と呼んだ。私にはちょっと疑問だが、一つは街が小さいことにある。人口は今でも70万人。以前は間違いなくシベリアの中心都市だったが、今では~~スクと名が付く街が育ってきた。
ふと思った。「スク」とは城壁か。そう言えば沖縄では「城」を「グスク」と言う。日本の縄文人が弥生人に押されて北と南に分かれたことはよく知られている。そしてその縄文人は、シベリアのかなりの部分を支配していたブリヤート人などと繋がりがある、同じだという学説もあるそうだ。
壮大な話だが、素人の私には「スク」と「グスク」から勝手な想像をするしか能がない。いつか調べたい。と思って、ターニャに聞いたら、「スク」とは、ロシア語の語尾変化の一種で、意味はないという。あーあ、大発見だと思ったのに。(笑)
冬は寒いらしい。特に一昨年はマイナス40度があったそうな。しかしガイドのターニャが、「日本ほど寒く感じない」と言う。彼女の言葉をそのまま引用すると、「湿気が日本は高い」「イルクーツクは湿気が低い」と言う。確かに今朝シャワーを浴びて頭をシャンプーしたが、見る間に乾いた。頭の毛を短くしたことは確かだが、これには驚いた。
雪はあまり積もらないそうだ。だから、車は「冬タイヤ」を10月頃に付けて、翌春まで。
「家の中は冬でもとても温かい」
「だから、イルクーツクに来る観光客は、冬の方が多い」
「昔は日本人が多かったが、最近は韓国、中国の人が多い。特に中国人は良いホテルに泊まる」
「ヨーロッパからはドイツ人」
と彼女は言う。もう一つ彼女の言葉で面白かったのは、アメリカ大陸では白人とインディオが激しい戦いを展開した。しかし、ロシア人とブリヤートなど現地人はあまり対立しなかった、という。互恵的であったのだ。
ロシア人は農業を得意とし、その産物をブリヤート人に提供した。農機具などを含めて。対して狩猟民族のブリヤート人(その他にも民族はいっぱいあるらしい)は、ロシア人に毛皮などを提供した。
イルクーツクには雑多な顔をした人がいる。民族の数は半端ではないそうだ。まあ、エリツィンを見てウクライナの人々が「あいつはアジア人だ」と言った話は頷ける。先にバイカル湖は「日本の本州の形によく似ている」と書いたが、ターニャが面白い神話を教えてくれた。
むかし極東には島がなかった。そこで神は今のバイカル湖の部分を切り取って、今の日本の位置に島を作った。それが日本だ、という話だった。ははは。実際にはバイカル湖の大きさは、日本の東京から青森に相当する。小さい。しかし、形は本当に良く似ている。