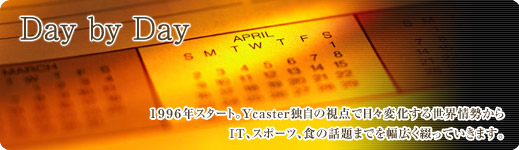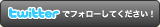(21:45)今週は暇を見ては中東の勉強をしています。月曜日に中東調査会主催の小杉 泰・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授の講演を聴いたのがきっかけ。私の場合一番知識の蓄積、取材経験の弱い地域で、どうしても分析が散発的になる分野。この地域に関する勉強会があるとなるべく出かけるようにしているのです。
小杉教授の話は、「最近のイスラーム復興運動の台頭」と題するもので、私にとって非常に面白かったのは
- イランのイスラム革命が起きたのが1979年で今年はちょうど30年になるが、重要な視点はその後もイランは革命状態を続けていることで、この”継続”ということが今のイスラム世界の大きな潮流を考える上で重要だし、その後のアルカイーダやタリバンの動きを考える上でもポイントになる(過激派に対する支持は減っているという現実を踏まえても)
- インドを中心にして考えると、インドの東(東南アジア、東北アジアなど)ではまず戦争が起こりえない状況が生まれているのに、インドの西について言えば紛争地帯が増える状況になっている。第二次世界大戦以降の推移を振り返れば、それは「危機の一重円」(パレスチナ問題とそれを契機とする戦争、イラク・イスラム革命以前)→「危機の楕円構造」(湾岸にも危機が起きてそれが二つ目の危機の源泉となって、二つの危機が楕円形で繋がった状態)→「危機の帯状化」(先生は「危機の楕円構造の三重中心化」と呼んだが、私は「帯状化」の方が良いと思う。二つの危機の源泉を残したままでのアフガニスタンでの危機の発生を指す)という動きになっている
- この「危機が帯状化した」中東での危機・問題の一気解決は非常に難しい課題となりつつあり、戦後一貫して中東の危機対処の先頭に立ってきたアメリカのオバマ政権は「まずはアフガニスタンでの危機脱出」を狙っているが、アフガニスタンやあえて言えばパキスタンでは「一体誰が誰なのか?」という問題を含めて非常に難しい対応を迫られている
「テクノロジー(技術体系)としてのイスラム」という話も面白かった。イスラム金融やハラール・ビジネスに関わる部分で、シャリア法などが関わってくる。実はイスラム金融もハラール・ビジネスもイスラム社会の人口が増えて、また石油価格の大幅な上昇の中で世界における地位は非常に上がっている。それをどう考えるか、という大きな視点があった。
私からは先生に二つ質問しました。「人口爆発、石油の富を背景とした今のイスラム世界の力のその後」と「インドが分水嶺になっているが、そのインドが1億人のイスラム教徒を抱えていることの問題点、特にムンバイの事件に関連して」でした。この二つは面白い視点を含んでいると思いました。
私がイスラム世界を考える上で、繰り返し思い出す言葉があります。それは、マハティール前マレーシア首相のもので、彼は『逆行が「苦境」をもたらした』と指摘して、確か2005年11月26日の朝日新聞「私の視点」に次のように見解を表明していた。彼は「イスラム世界の苦境」を以下のように分析していた。
- 今やイスラムはかつて世界において担っていた役割を果たせずに、代わりに弱体化し迫害されている。スンニ派とシーア派の対立の根は深い。その他の宗派の数も多い
- 最大の問題は、イスラム教学およびイスラム式の生活が現代世界からますます乖離していることにある。コーランを解釈する者たちが宗教の枠内でその法や実践を学んでいるため、今日の科学的な事象を理解できないことが多い
- かつてイスラム教徒達は見識を積んだ故に力があった。ムハンマドの教えは、読めということだが、コーランには何を読むべきかは示されていない。実際、当時は「イスラム教学者」なる者は存在しなかったから、読めとは、すなわち何であれ読むようにと言うことだった。だから初期のイスラム教徒は偉大なギリシャの科学者や数学者、哲学者たちの著書を読んだ。ペルシャ人やインド人、中国人たちの著書からも学んだのである
- その結果、科学や数学の知識が開化した。イスラムの学者達は天文学、地理学、数学の新分野などの専門領域を発展させた。アラビア数字を発展させ、無限の計算でも簡単にできるようにした
- ところが、イスラムの有識者たちは15世紀ごろから科学的な研究を抑制し始めた。彼等は、特にイスラムの法体系を学ぶ者だけが死後の勲功を享受できると主張し、宗教のみを学び始めたのだ。一方、ヨーロッパでは科学や数学的な知識への信奉が始まり、ルネサンス期を迎えていくのに、イスラム世界は知的後退期へんと向かった。そうした視野の狭さが、今日のイスラム教徒の苦境を招いたのである
マハティールが当時、今のイスラム世界に宗教指導者の知的怠慢に関して、「ある宗教指導者は、人が月に着陸したことを信じなかった。他の指導者は、地球は2000年前に生まれたと言い張る」と述べていたのは今でも思い出す。
中東に関しては、ちょうど目の前に「まるごとわかる 中東経済」(日本経済新聞社)という本があったので、それも読み始めています。まあちょっと古い、情勢が変わってしまう前の本なんですが。
あそれから、新しいエッセイが公開されました。風力発電に関するエッセイです。